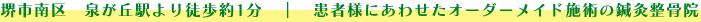捻挫した時はどうすれば?正しい対処法も解説
2025.03.05

日常生活でのちょっとした不注意や激しい運動など、さまざまな場面で捻挫のリスクは潜んでいます。捻挫を悪化させないためにも、正しい方法で対処することが重要です。今回は、捻挫をしたときにやってはいけないことや対処法について紹介します。
堺市南区泉ヶ丘にあるきぼう鍼灸整骨院では、身体のさまざまなお悩み・ご質問等の相談も承っていますのでお気軽にご相談下さい。
御予約はこちらから24時間受付中です。https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000624316/
他の方はコチラもよく読まれています➡リュックの背負い方で姿勢が悪くなる!?正しい背負い方とは?

目次
捻挫をした際にやってはいけない3つのこと
捻挫をした際、治そうとして行っていたことが、かえって悪化を招く要因になる場合があります。ここでは、捻挫をしたときに避けるべき行動について解説します。
1.無理に動かす・負荷をかけること
骨折と比べて捻挫をしたときは、痛みがあっても日常生活は問題なく送れることがあります。早く捻挫を治したいという気持ちから、無理をして動いてしまう方もいるでしょう。
しかし、負傷している足に負荷をかけるのはおすすめできません。痛めている部分を無理に動かすことで、痛みや腫れが悪化する可能性があるからです。また、患部をかばうような歩き方をしていると、ほかの部分に負担がかかり別の場所も痛めてしまうおそれがあります。
2.患部をマッサージすること
捻挫をしたとき、マッサージをして痛みを和らげたい、腫れをひかせたいと思う方もいますが、安易にマッサージをするのは危険です。マッサージやストレッチをすると血行が良くなりますが、炎症が悪化して腫れや痛みが酷くなる可能性があります。
また、湯船に浸かって必要以上に温めたり、冷やしたりすることも控えましょう。特に、腫れや炎症が続いているうちは、温めないことが肝心です。
一方、冷やし過ぎると血行不良を招きやすくなります。負傷した部位の治りが遅くなることがあるため、状況に合わせて対処することが大切です。
3.痛みが長引いているのに放置する
3週間以上痛みが続いていたり、足に違和感があったりする場合は、一度整形外科へ受診することをおすすめします。
痛みがあるにもかかわらず放置すると、後遺症が残るおそれもあります。違和感があるときは自己判断せず早めに対処してください。また、一人で歩くことができず、激しい痛みを伴う場合は、骨折している可能性があるため注意が必要です。
捻挫をしたときの正しい対処法

足の痛みや腫れが気になるときは、正しい方法で対処することが大切です。ここでは、捻挫をしたときに役立つ対処法について解説します。
安静にする
痛みを我慢して負傷した部位を動かそうとすると、腫れがひどくなったり、捻挫が長引いたりする可能性があります。
怪我をした直後は足首に負荷がかからないように座ったり、横になったりするなど、安静にすることが重要です。また、サポーターやテーピング、包帯などで足を固定すると、足への負担を軽減できます。
患部を冷やす
捻挫をしたときは、湿布や水で濡らしたタオルなどを使い、足首を冷やすことも有効です。冷やすことで患部の炎症を抑える効果が期待できます。
ただし、直接氷を肌につけたり、長時間冷やしたまま放置したりすると、凍傷になるおそれがあります。10~15分程度を目安に患部を冷やしましょう。患部を氷で冷やす場合は、肌に直接触れないようにビニール袋やタオルなどで包むことをおすすめします。
患部を圧迫する
弾性包帯などを使用して、患部を圧迫するのもひとつの方法です。足を痛めた部分を圧迫することで、腫れや内出血を抑える効果が期待できます。
ただし、強い力で圧迫すると、かえって血行不良を引き起こしかねません。足のつま先が青紫色になっていたり、しびれがみられたりする場合は、手の力を緩めて様子を見てください。
患部を高くする
捻挫をした箇所に腫れがみられる場合は、その部分が心臓の位置よりも高くなるように調整しましょう。患部を高くすることで、腫れや内出血を防ぐ効果が期待できます。
足の高さを調整するために、床やベッドの上に横になり、痛めた部分の下にクッションや座布団などを敷くなど工夫しましょう。
捻挫の予防法

何度も捻挫を繰り返す方や、捻挫の心配をせずに安心して運動したい方は、普段からちょっとしたコツを試すことで、捻挫を予防することができます。ここでは、足の捻挫を予防する5つの方法を紹介します。
ウォーミングアップを行う
運動不足の方が急に運動し始めたり、激しい運動をしたりすると、関節を痛めやすくなり、捻挫のリスクが高まります。身体が思うように動かずに転倒してしまうこともあるかもしれません。
運動する前は必ずウォーミングアップを行いましょう。ふくらはぎやハムストリングの筋肉をほぐすためのおすすめのストレッチのやり方は下記の通りです。
1.両足を肩幅に開いて立つ
2.右手と左手でそれぞれ右足首と左足首をもつ
3.深く息を吸いながら、ゆっくりと膝を曲げていく
4.深く息を吐きながら、元の姿勢に戻す
5.2~4を1セットとして10回ほど繰り返す
正しい姿勢を心がける
姿勢が悪いと身体の軸がずれてしまい、些細なことで転んでしまうことがあります。足首に余計な負担がかかり、捻挫のリスクも高まるため、正しい姿勢を心がけましょう。
特に、足首は身体のバランスを保つ上で重要な役割があります。普段から姿勢を正すことで、自然と捻挫予防につながります。
とはいえ、自分では正しい姿勢がわからないという方もいるでしょう。そのような場合は、早めに整骨院などでメンテナンスしてもらうことをおすすめします。
サイズの合った靴を履く
捻挫を予防するために、足のサイズに合った靴を履くことも意識しましょう。足に対して靴のサイズが大きすぎたり、小さすぎたりすると、靴擦れや捻挫などを引き起こしやすくなります。
特に、ヒールの高い靴を履いていると、足首が不安定になり、捻挫のリスクを高めてしまいます。 場面に合わせてスニーカーやローヒールの靴を選ぶのも良いでしょう。
仕事で履く機会がある場合は、移動中だけでも足に負担がかからない靴に履き替えることをおすすめします。
サポーターやテーピングを使用する
捻挫しやすい足首などを、あらかじめサポーターやテーピングで保護しておくと、怪我を予防できます。しっかりと足首を固定することで、安定感が増して捻挫を防げるからです。特に、頻繁に捻挫しやすい方は、サポーターやテーピングを積極的に活用してみましょう。
足首の柔軟性を高める
足首の柔軟性を高めると、捻挫のリスクを下げることができます。おすすめの柔軟性を高めるストレッチのやり方は下記の通りです。
1.椅子に座り、右足を折り曲げて左膝の上に置く
2.右足の指に左手の指をそれぞれ交互に挟み込む
3.足首をくるくると回す(右回り、左回りともに行う)
4.左足も同様に1~3の順に行う
捻挫の痛みが引かない場合はきぼう鍼灸整骨院へご相談ください
整形外科を受診して捻挫が良くなったはずなのに、足に違和感があるといつまでこの状態が続くのか、治る見込みがあるのか不安になる方もいるでしょう。そんなときは、きぼう鍼灸整骨にご相談ください。
堺市泉ヶ丘のきぼう鍼灸整骨院では、一人ひとりの身体の状態に合わせて施術を行っております。捻挫以外にも、肩こりや腰痛、頭痛、ぎっくり腰など、さまざまな身体の悩みに対応可能です。
痛みが苦手な方でも受けられるので、初めての方でも心配ありません。家庭で簡単にできるストレッチ方法も指導しているため、いつでもどこでもセルフケアを続けられるメリットがあります。足首の状態が気になる方は、お気軽にきぼう鍼灸整骨までお問い合わせください。
まとめ
捻挫をしたときの対応次第で、早く治ることがあれば、なかなか治らないこともあります。怪我をしたときは、患部をマッサージしたり、無理に動かしたりするなどの対処は厳禁です。
正しい対処法を試しても痛みが長引いている場合は、放置せずに整形外科への受診を検討しましょう。