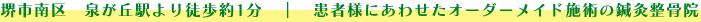整骨院でも交通事故の治療期間の目安は?打ち切りを打診された際の対処法も解説
2025.07.23

交通事故で怪我をしたときは、整骨院で治療を受けることができます。治療期間中にかかった費用を加害者側の保険会社に請求できます。しかし、保険会社が治療の途中で支払いの打ち切りを打診してくることもあるため、対応には注意が必要です。
24時間ご予約できます→https://pq87obh2.autosns.app/line
今回は交通事故による怪我の治療期間の目安、治療を打ち切るタイミングを紹介します。あわせて、保険会社から治療の打ち切りを打診されたときの対処法も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
整体を利用するメリットとは?病院や整骨院との違いも解説
目次
交通事故の怪我の治療期間の考え方

交通事故による怪我の治療期間とは、事故に遭い治療を始めてから、完治または症状固定に至るまでの期間をいいます。症状固定とは、怪我が完全に治ったとはいえないものの、これ以上治療しても改善が見込めない状態のことを指します。
治療期間は、保険会社の治療費の支払いの基準になるため重要です。治療期間中にかかった費用は加害者側に請求でき、保険会社が一括対応で直接病院に支払います。
また、治療期間は保険会社が支払う入通院慰謝料を算定する基準にもなります。治療期間が長引けば費用がかかるため、その分支払われる金額が大きくなるのです。
交通事故による怪我の治療期間の目安

怪我が完治、症状固定するまでの期間は、個人差が大きいものです。怪我の内容や重症度、回復具合によっても期間が変わります。
交通事故の怪我には「DMK136」と呼ばれる治療期間の基準が設けられています。保険会社が治療期間を判断する際に目安とするのは、次の日数です。
・D(打撲)の治療期間の目安は1か月
・M(むちうち)の治療期間の目安は3か月
・K(骨折)の治療期間の目安は6か月
それぞれ詳しくみていきましょう。
なお、交通事故で怪我をした場合でも、整骨院でケアを受けられます。
打撲(D)の治療期間の目安は1か月
打撲は痛みや腫れが治ったら完治とされ、治療期間の目安は1か月です。打撲は交通事故の怪我の中では軽傷に分類されます。主な受傷原因は、事故の際に車のハンドルや扉にぶつかった、二輪車で転倒したなどです。
むちうち(M)の治療期間の目安は3か月
交通事故に起因するむちうちの治療期間は、3か月が目安です。むちうちとは頚部外傷全般を指す言葉で、診断書に書かれる医学的な傷病名は次の通りさまざまです。
・外傷性頚部症候群(頚椎捻挫・頚部挫傷)
・神経根症(頚椎椎間板ヘルニア・頚椎症性神経根症)
・脊髄損傷 など
むちうちは首まわりに強い衝撃がかかって生じる怪我で、しびれや痛みが後遺障害として残ることがあります。
骨折(K)の治療期間の目安は6か月
骨折は交通事故の怪我のなかでも重傷に分類され、治療期間の目安は6か月です。交通事故では、次のようにさまざまな部位が損傷します。
・指
・脚
・鎖骨
・肩甲骨
・胸骨
・肋骨
・骨盤
・大腿骨
・頭蓋骨など
目安は6か月でも、骨折の治療期間は事故の状況や部位によってさまざまです。大きな骨で治りにくい場合、損傷が非常に細かく治癒が難しいケースもあります。
交通事故による怪我の治療を終了するタイミング

交通事故の治療を終了するタイミングは、医師の判断によります。怪我の状態を診断し、完治・症状固定の判断ができるのは、国家資格をもつ医師のみです。同様に、医師は保険会社に提出する診断書を作成する役割を担っています。
交通事故による怪我の治療が長引いても、自己判断で通院を中断するのは危険です。再発や悪化のリスクがあるだけでなく、保険会社から支払われる慰謝料が減額されるケースもあります。症状が落ち着いて通院を中断したい場合は、まず医師に相談しましょう。
治療費の打ち切りを打診されることもある

「DMK136」で目安とされている治療期間を経過しても、まだ治療が必要な場合があります。しかし、相手の保険会社から治療費の支払い打ち切りの提案を受けることもあります。
ここでは、その背景や打ち切りを判断されるポイントをみていきましょう。
打ち切りを打診する背景
保険会社が治療費の支払いを打ち切る背景には、契約に基づく合理的な判断が関与しています。
例えば、治療が「症状固定」と判断されると、保険契約上、支払いの終了が適切とされる場合があります。
また、自賠責保険には傷害部分に対する支払い上限が120万円と定められており、保険会社はこの範囲内での支払いを目指します。
さらに、過剰な治療費の支払いを防ぐため、保険会社は通院頻度や治療内容の妥当性を検討し、必要以上の支出を抑制しようとします。
これらの判断は、保険契約に基づくものであり、保険会社の立場としては合理的な対応といえます。
打ち切りを判断されるポイント
「DMK136」で目安とされている治療期間の経過に加えて、通院頻度も打ち切りの判断材料として加味されています。通院頻度が低い場合には、本当はもう回復していて痛くないのではないかと思われてしまうことがあります。
1か月に1回や隔週などの頻度で通院している場合には、少なすぎると判断されてしまうでしょう。
漫然治療と思われる場合も、打ち切りを判断するポイントのひとつです。同じ医薬品の処方を繰り返し受けていた場合には、必要な治療ではないと判断されることがあります。
また、定期的な医師の診察を受けておらず、マッサージや整体ばかり受けている場合も、もう回復していると判断されやすいです。
治療費の打ち切りを打診された場合の対処法
保険会社から一括対応打ち切りの連絡があっても、実際にはまだ治療が必要な状態というケースも珍しくありません。そのような場合には、まだ治っていないにもかかわらず、治療の継続が難しくなってしまいます。
では、保険会社から治療の打ち切りを打診された場合にどう対処すれば良いのかみていきましょう。
安易に打診に応じない
安易に保険会社の打診に応じるのは危険です。打ち切りを受け入れてしまうと自己負担が大きくなり、治療やケアが継続できなくなるリスクがあります。通院期間や日数が減ったために受け取れる慰謝料が減り、不利になる可能性も高いのです。
治療が突然打ち切られたことで、後遺障害等級認定において不利になる可能性もあります。治療の打ち切りは、怪我が完治・症状固定していることが大前提です。保険会社から打診されたらまずは医師に相談し、治療終了かどうか確認しましょう。
医師が治療終了を判断しない限りは治療を続ける
保険会社が打ち切りを通告してきても、医師が治療の継続を勧める場合は指導に従う必要があります。受傷程度や身体の状態を診断し、必要な治療の指示を出せるのは、国家資格をもつ医師だけです。
保険会社が必要性を認めなくても、医師が勧めるのであれば治療は継続すべきです。保険会社に現状や医師の指導内容を説明して、治療期間の延長を交渉しましょう。
保険会社が交渉に応じないからといって、あきらめる必要はありません。いったん自己負担の立て替え払いで治療を継続し、最終的な示談のタイミングでまとめて請求する方法もあります。治療にかかった費用を明らかにするためにも、通院した際の領収書は確実に保管しておきましょう。
交渉が難しい場合は弁護士に相談する
治療の延長を保険会社と交渉するのが難しい場合は、弁護士に相談してください。保険会社が治療費の支払いを拒否している、減額を譲らずにトラブルに発展した場合でも、弁護士が間に入ればスムーズに解決を目指せるのでおすすめです。
弁護士は医師と連携して、保険会社との交渉を代行します。面倒な書類作成や提出、保険会社からの電話対応もすべて任せられるので、負担を大きく減らせます。保険会社が適切な支払いに応じない場合は訴訟等の対応もとれるので、まずは相談してみましょう。
治療期間が終わった後に後遺症が残った場合は?
治療期間終了後も後遺障害が残る場合があります。その場合、後遺障害等級認定を申請することで、加害者に対して後遺障害慰謝料や後遺障害による逸失利益を請求することが可能です。
手続きを行う際には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
事前認定は、加害者の保険会社が手続きを行う方法です。申請書類や資料などは保険会社が用意するため、被害者にとっては手間がかかりません。しかし、被害者本人が資料の選定や記載内容に関与できないのがデメリットです。有利な資料を提出できず、認定を受けられない可能性もあります。
これに対して被害者請求は、被害者が自ら手続きを行う方法です。カルテなどの資料も自ら揃えなければなりません。手間がかかるのがデメリットですが、有利な資料を提出できるメリットがあります。
例えば、日常生活における支障や痛みなどを証明するための陳述書や、事故現場や事故車両の写真などです。事故の衝撃の大きさや被害者の状況も適切に主張できます。
まとめ
交通事故による怪我の治療期間は、治療を始めてから完治、または症状固定に至るまでの期間を指します。
突然保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合は安易に受け入れず、医師に相談した上で保険会社に治療期間の延長を交渉するようにしましょう。
医師の許可があれば、交通事故後のケアは整骨院でも受けられます。治療期間が終了した後のメンテナンスに、定期的に通うのもおすすめです。
きぼう鍼灸整骨院でも、交通事故のケアに対応しています。自賠責保険による施術が可能であり、窓口負担は原則0円です(※)。転院・整形外科との併用もできるため、交通事故による負傷にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。