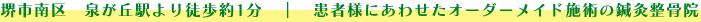首を回すと音がする原因と対処法とは?改善するストレッチも紹介
2025.02.25
デスクワークをしている方が気になる症状のひとつに、首を回したときの音があります。なかには「大きな病気が隠れているかもしれない」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、首を回すと音がする原因と対処法や、首の不調を改善するストレッチを紹介します。
目次
首を回すと音がするのはなぜ?考えられる原因

首を回したときに聞こえる「ゴリゴリ」や「ポキポキ」という音は、首の関節や筋肉に起因していることが一般的です。
加齢とともに首の関節にある軟骨が徐々にすり減ると、音が鳴る場合があります。軟骨には関節のクッションとしての役割があります。そのため、すり減ると骨同士が直接こすれてしまい、首を動かしたときに音が鳴りやすくなるのです。
首まわりの筋肉の緊張や硬さも、音が鳴る原因といわれています。特にデスクワークで同じ姿勢を長時間続けると、筋肉が緊張して固くなり、首を動かしたときに音が鳴りやすくなります。
首を回したときの音は多くの場合、深刻な問題ではありません。しかし、痛みを感じたり頻繁に音が鳴ったりする場合は、何らかの病気が隠れている可能性があります。
堺市南区泉ヶ丘にあるきぼう鍼灸整骨院では、身体のさまざまなお悩み・ご質問等の相談も承っていますのでお気軽にご相談下さい。
御予約はこちらから24時間受付中です。https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000624316/
他の方はコチラも読まれていますスマホ首がつらい!スマホ首の改善方法と整骨院に相談するメリット
首を回した際に出る音は病気の可能性もある?

首を回したときに音が鳴るだけであれば、病気の心配はあまりありません。しかし、音以外に下記の症状が現れる場合は注意が必要です。
・首を動かす際に痛みを感じる
・手や指先にしびれや痛みを感じる
・歩く際にふらつきや脚の脱力感がある
・ボタンの留め外しや箸を使うなど、手先の細かい動きが難しい
これらの症状は首の骨に異常が生じ、手や脚へ向かう神経を圧迫することで起こるとされています。
考えられる病気として、下記の4つがあげられます。
・頚椎症
加齢による首の骨の変形や、椎間板(ついかんばん:首の関節にあるクッション)の変性が起こり、痛みが生じます。
・頚椎症性神経根症(けいついしょうせいしんけいこんしょう)
頚椎症によって神経根(首の神経の根本)が圧迫され、首の痛みや肩~腕~手にかけてのしびれや痛みが広がります。症状は片側に出るのが特徴です。
・頚椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう)
頚椎症によって脊髄(首の骨にある穴を通る神経の束)が圧迫され、両手、両足のしびれや動きにくさ、排尿や排便の異常、歩きにくさなどの症状が生じます。
・頚椎椎間板ヘルニア
椎間板が後方へ飛び出し、神経根や脊髄を圧迫して首や肩、腕の痛みが生じます。症状が進むと手足の動きやしびれも現れます。
首を回した際に痛みや違和感がある場合は、症状が悪化する前に整形外科を受診し、専門医による診察を受けてください。
首の不調が気になった際に心がけておきたい生活習慣

首の不調が気になるときは、下記3つの生活習慣を心がけてみてください。
首を鳴らすクセをやめる
首を鳴らすクセがある方は、無理に鳴らさないようにしましょう。首を鳴らすクセがついていると、痛みや不調を引き起こす可能性があります。具体的には、下記の症状が考えられます。
・過度に首を回すと筋肉や靭帯に負担がかかり、首の可動域(動く範囲)が狭くなる
・椎間板のなかにある髄核(ずいかく)という物質が飛び出し、神経を圧迫して痛みやしびれなどが生じる
首の可動域内で自然に動かすことを心がけ、引っかかる感じや痛みなどがある場合は、無理に動かさないようにしましょう。痛みが出ない範囲でストレッチをして、首の筋肉をリラックスさせることが大切です。
姿勢を正す
首や肩などにかかる負担を減らすため、姿勢を正しましょう。長時間のデスクワークで猫背や前傾姿勢になると、首や肩に過剰な圧がかかり筋肉の緊張が続くため、痛みやコリが起こります。これは緊張状態によって血流が悪くなり、疲労物質が溜まるからです。
正しい姿勢とは具体的に、頭が背骨の真上にくるように軽く顎を引いて立つことです。耳・肩・股関節・膝関節・外くるぶしが一直線になるのをイメージしましょう。正しい姿勢を意識すれば首にかかる負担が減り、筋肉の緊張が和らぎます。
重い物を持たないようにする
重い物を持つと首に過度な負担がかかるため、できるだけ避けましょう。特に片側だけで持つ習慣がある方は注意が必要です。
例えば、右手で重い物を持つと、身体はバランスを取るために左側に傾きます。このように不自然な姿勢が続くと、首の筋肉に疲労が蓄積し、痛みを感じることがあります。
そのため、重い物を持つ場合は、持ち手を頻繁に替え、左右でバランスよく負担を分散させましょう。また、こまめに休憩をとって首の筋肉を休めることも重要です。
もし重い物を持ったあとに首の痛みやしびれを感じたら、早めに整形外科を受診し、症状の原因を確認してもらいましょう。
首の不調を改善するためのストレッチ
首の不調を改善するために、次に紹介する3種類のストレッチを実践してみてください。これらのストレッチにより首まわりの筋肉がほぐれ、関節の可動域が広がったり音の発生を減少させたりといった効果が期待できます。
胸鎖乳突筋ストレッチ
胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)は、胸や鎖骨から首の前を通り、側頭部へとつながっている筋肉で、首を支える役割があります。
この筋肉をストレッチして、デスクワークで負担がかかっている首の不調を改善しましょう。
【手順】
1.片手で反対の肩を上から押さえる
2.肩を押さえながら斜め後ろを見上げる
3.押さえている肩と同じ側の首の前面が伸びているのを感じながら20秒以上キープする
4.ゆっくりと元の姿勢に戻る
同様の手順で反対側も実施し、左右をバランスよくストレッチします。
テニスボールでストレッチ
テニスボールを使ったストレッチで首の後ろにある筋肉をほぐし、血行を改善しましょう。
【手順】
1.テニスボール2つをテープやひもなどで固定する
2.仰向けに寝て、首の付け根にテニスボールを当てる
3.ボールが左右の筋肉に均等に当たるように調整する
4.気持ちよいと感じる強さで30秒程度キープする
首の前方から側方には脳に向かう太い血管があるため、テニスボールを当てるのは首の後方のみにしましょう。また、後方に当てていても強い痛みを感じた場合はすぐに中止してください。
背伸び
デスクワークでは前傾姿勢になりやすいため、背伸びをして身体をしっかり伸ばしましょう。
【手順】
1.手首を手の甲側に反り、大きくバンザイしながら天井を見る
2.この姿勢を20秒キープする
30分に1回くらいの頻度で行うのがおすすめです。
まとめ
首を回したときの音は関節や筋肉に起因しており、多くの場合深刻なものではありません。
しかし強い痛みやしびれ、手や脚の動きづらさを感じた場合は、何らかの病気が隠れている場合があります。その際は整形外科を受診し、専門医に診察してもらいましょう。
堺市のきぼう鍼灸整骨院では、お客様一人ひとりに合わせた施術と、生活習慣を改善するアドバイスをしています。施術後はご自身で管理できるようにお手伝いしていますので、首の不調が気になる方はぜひきぼう鍼灸整骨院へお問い合わせください。